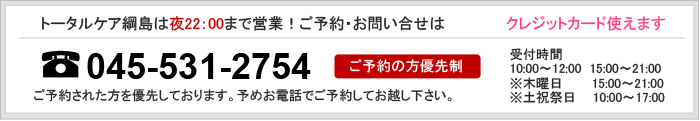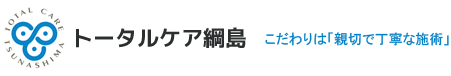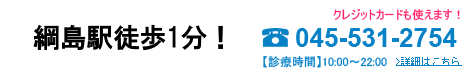新着情報
2017/10/25
副鼻腔炎を治療しないと?
鼻水だけでなく、頭痛や歯痛、そして慢性化すれば
疲労感や集中力の低下にもつながってしまう副鼻腔炎。
できるだけ慢性化しないうちに治したいですよね。
とはいっても、もともとが風邪が長引いてしまったことが原因。
免疫力が低下してしまっているので、きちんと治療しないと治りません。
副鼻腔炎がさらに別の病気を引き起こしてしまうこともあります。
鼻はさまざまな大切な器官と繋がっていますが
そこに炎症が波及してしまうと、重い後遺症が残ることも!
例えば目。目の疲れや痛み、涙が止まらないなどの症状の他
視力障害が起きてしまうことも!
脳に波及すれば、髄膜炎などにより麻痺や意識障害が起きたり
ひどい場合には死に至るケースもあるのです!!
たかが風邪、たかが鼻水と侮っていると大変なことに!!
次回は、どんな治療が必要なのかをお話ししていきます。
2017/04/28
つわり(妊娠悪阻)に鍼灸治療!
先日久しぶりに会った友達から
「最近体調良くないんだよね…実はつわりで…^^;」と相談を受けました。
妊娠は、ご本人にとっても周りの方々にとっても嬉しいことです。
ですが、ホルモンバランスであったり
出産に備えてお仕事などの調整が必要であったりと
さまざまな変化に見舞われ、体調を崩してしまいがちです。
つわり(妊娠悪阻)は、まったく起こらない人もいますが
中には食事が摂れず体重がすごく減ってしまったり脱水を起こしたりして
入院治療が必要な場合もあります。
何度も嘔吐してしまうような場合にはまず病院への受診が必要ですが
眠気がすごい、だるい、吐き気がある、匂いに敏感になる…
大抵はこういった症状と何とか折り合いをつけていくことになります。
では、このようにつわり(妊娠悪阻)で体調が悪いときには
どう対処すれば良いのでしょうか?
普段であれば、ちょっとした風邪や頭痛といった不調に対し
市販薬などの服薬を第一選択にされる方も多いと思いますが
お腹の赤ちゃんへの影響を考えると、妊娠中の服薬には慎重にならざるを得ません。
(もちろん、産婦人科の先生に相談してみることはおススメです)
しかも、つわり(妊娠悪阻)の場合は原因がはっきりしないため
この薬を飲めばスッキリ治っちゃうよ!!というわけにはいきません。
身体がつらいのに加え、ホルモンバランスの変化で気分が沈みやすく
無事に産まれてきてくれるかな…という不安が押し寄せてきたりして
心にも大きな負担がかかってしまうこともあります。
けれど、きっと妊娠された方の誰もが、できることなら
授かった幸せをゆっくり噛みしめて過ごしたい…と思われているはず。
そこでお役に立てるのが、鍼灸治療なのです!!
私の友達も「え?鍼灸?!効くの?」と驚いていましたが
実際につわり(妊娠悪阻)が軽減した例がたくさんあります!
ゆっくり幸せを嚙みしめたい…!という方はもちろん
産休入るまでお仕事頑張らなくちゃ!家事も頑張らなくちゃ!
二人目(三人目以降も)だから上の子の面倒も見なきゃ!
とゆっくり休んでいられない方にも、ぜひおススメです!
次回は、もう少し詳しいお話をしたいと思います~^^
2017/04/17
赤くならないためだけではない!日焼け止めの効果
海や山など屋外へのお出かけの際に活躍する日焼け止め。
赤くなってヒリヒリ…後日黒くなって皮がむけてきちゃった…
なんてことがないよう、しっかりと塗っておきたいものです。
しかし、日焼け止めの効果はこのような炎症を防ぐだけではないのです!
炎症を引き起こすのは、紫外線の中でも『B波』と呼ばれるものですが
これは、地表に届く紫外線のわずか5%です。
皮膚表面の表皮に強く影響し、ヒリヒリ(サンバーン)や
黒くなる(サンタン)状態を引き起こします。
『B波』だけではなく、『A波』というものもあります。
エネルギーは強くないのでB波のように目に見える変化は起こしづらいですが
照射量が多く(紫外線の95%)、また浸透力が高いので、皮膚の深くの真皮層まで影響します。
なんと皮膚表面に届いた『A波』の2~3割が、真皮にまで到達するといわれています。
真皮には、お肌の弾力のもとであるコラーゲンやエラスチンが存在しますし
またそれらを生み出す線維芽細胞もありますが、これらが『A波』によって損傷を受けます。
これが、シワやたるみの原因になってしまうのですね!!
もちろん、表皮の最下層、真皮の近くにあるメラノサイトにも影響し
メラニン色素の生成を増やして、シミの原因にもなってしまいます!
サンバーン・サンタン→B波
シミ・シワ・たるみ →A波 ということです。
ちなみに、B波の予防効果はSPF値で(数字なのでわかりやすい)。
A波の予防効果はPA値で(+表示なので少し地味…)わかるようになっています。
効果が高いと、お肌への影響も強くなってしまうので
生活状況に合わせて日焼け止めの種類を選び、しっかり塗っていきましょう^^
2017/04/15
紫外線対策は万全?正しい日焼け止めの塗り方
紫外線対策には、まず日焼け止め!
なのですが…皆さんは正しい塗り方、できているでしょうか?
よくやってしまいがちなのが、朝塗った後は塗り直さない…なんてこと。
日焼け止めの説明書きに「2~3時間ごとに塗り直してください」と書いてありますが
お仕事やお出かけの合間に、何度もメイクを落として塗り直すのはなかなか至難の業ですよね。
もちろん、長時間の屋外へのお出かけの場合は、メイクを落とす手間をかけてでも
しっかりと塗り直したほうが紫外線対策としては効果が高いのですが…
忙しかったり、屋内で過ごすことが多い場合は、少し手間を省くことができるのです!
では、どうやったらこまめに紫外線対策できるのでしょうか?
オススメなのは、パウダーファンデーション。
ファンデーション自体に紫外線を防ぐ効果があるものをお使いの方は多いと思いますが
「リキッド」ではなく「パウダー」というのがポイントなのです!
実は、パウダーファンデーションの粉が、紫外線を跳ね返してくれるため
リキッドなどよりも効果的に紫外線対策ができるのです!
あぶら取り紙などで余分な皮脂を取り除いた後に、パウダーファンデーションをつけ
その後にポイントメイクをし直します。
これならば、クレンジング→乳液など→日焼け止め→メイクとするよりも
かなり時間短縮できるので、ちょっとした合間に塗り直すことが可能ですよね!
普段、リキッドファンデーションなどをお使いの方でも
もし紫外線対策にお困りでしたら、試してみる価値はあるかもしれません!
紫外線による「光老化」を起こさせないためにも
しっかりと紫外線対策を行なって、まず予防をしていきましょう!!
もうすでにできてしまったシミには、美容鍼もオススメです^^
2017/04/12
目指せ美肌!紫外線に注意!!
桜も咲き、いよいよ本格的な春がやってきました!
気温も上がってきたので、たくさんお出かけしたくなりますね^^
そんなこの季節のお出かけですが、
うっかりしていると大変なことに…!
何がかというと、、、そう、紫外線です!!!
以前にもお伝えしましたが、4月~5月の紫外線量というのは
日差しが強いなぁと感じる夏とあまり変わらないのです!
紫外線対策を怠ってしまうと「光老化」してしまうかも…!
※光老化…紫外線がシミ、しわ、たるみの原因となること
今回は、紫外線ダメージによってシミができてしまう
メカニズムについてお話していきたいと思います。
お肌は、表皮・真皮・皮下組織という層構造になっています。
表皮は、細胞が何層にも重なっていて、ターンオーバーをしているところ。
真皮は、コラーゲンやエラスチンが含まれる、弾力あるところです。
表皮と真皮の間に、メラノサイトというものがあります。
名前からわかるように、このメラノサイトが「メラニン色素」を作ります。
日常的に紫外線を浴びていると「メラニン色素」がお肌に溜まり
色素沈着、つまりシミになってしまう!というわけなのですね。
ちょっとくらいと油断せず、しっかりと紫外線対策をしていきましょう。
手軽な紫外線対策として、日焼け止めがありますが
次回はこの日焼け止めの塗り方について、おさらいしていきましょう!
ちょっと意外な対策もありますよ~^^