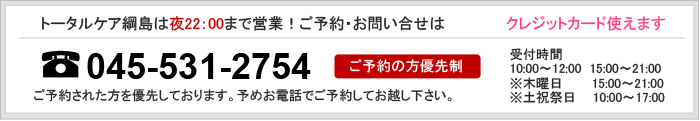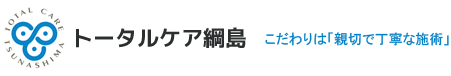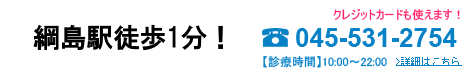新着情報
2021/09/25
脂肪太りの原因、湿とは??
お酒の持っている性質、“湿”について
詳しくお伝えします!
“湿(しつ)”は、湿度・湿気などの言葉にあるように
身体の中に溜まった、余分な水分を表しています。
お酒を飲みすぎたり、おつまみ(脂っこいもの)や
甘いものを食べすぎたりすると、この“湿”が溜まります。
余分な水分ですので、顔がパンパンにむくみやすくなります。
また、身体は何とか水分を外に出そうとするので
トイレが近くなったり、お腹がゆるく下痢になったりします。
お酒を飲みすぎても1~2日もすれば、身体の働きにより
むくみなどの症状は消えていきますが
頻繁にお酒を飲む方や一度に大量に飲んでしまったときには
身体の働きが追いつかなくなり、大きな負担となります。
体外に排出されなかった“湿”は、だんだんと
憎き、お腹などのお肉…脂肪へと変化してしまいます。
“湿”の処理能力は、個人差がありますし
日常の食生活によっても変化します。
お酒を飲んだあと、むくみなどの症状が強く出るようであれば
“湿”が処理できていない証拠。飲みすぎです!
コロナ禍の家飲みで、ついついお酒の量が
と増えるかもしれませんが、
少し自分の身体の状態を見つめてみてくださいね!
2021/09/11
胃腸の調子が悪いと、舌に出る?!
人に舌を見せる機会というのは、普通ならあまりありませんが
鍼灸治療を行う際にはお見せいただくことがあります(舌診)。
ちょっと恥ずかしいな…と思われる方もいるかもしれませんね!
ですが、舌を見ただけで体質がわかってしまうことがあるのです!!
特に胃腸の調子が悪いときには、舌に特別な変化が起こっています。
とはいっても舌は千差万別であり、なかなかご自分では
舌に起こっている変化に気づけないかもしれません。
そこで登場するのが、我々鍼灸師なのです!!^^
どんな感じの変化が起こっているかというと、
舌が通常よりも大きくむくんだような感じになっていたり…
舌の縁の部分に歯のあとがギザギザとついていたり…
こういうときには、胃腸(脾胃)に問題があるのです!
むくみやギザギザというのは、どちらも身体の中の水分が
異常に多くなっていることを示しています。
胃腸(脾胃)は、食べ物から栄養を吸収するだけでなく
水分も吸収して代謝していきます。
その働きが弱くなっていると、全身に余分な水分が溜まりやすくなり
それが舌にも反映されると、むくみやギザギザになります。
舌を見るだけで、胃腸をはじめとした
内臓(五臓六腑)の働きがわかってしまうのですね!!
本当かな…と疑いたくなるのですが、これも長い年月をかけて蓄積された
たくさんの経験から得た統計によるものなのです。
私もはじめは疑っていましたが(笑)、実際見ると嘘ではないのです!
ただ、先ほども述べた通り、ご自分では舌の変化に気づきづらいので
気になる方はスタッフまでお気軽にお声かけください~!
2021/09/04
ニキビをなくすには?その9
前回は、出すべきものが多すぎるタイプについてお伝えしましたが、
今回は、もうひとつのタイプについてご紹介したいと思います!
そのもうひとつのタイプとは…
出すべきものを外に出せないタイプです。
ちょっとモヤッとした言い方ですね(笑)
ターンオーバーが遅く、皮膚が厚いために、出しづらく
また、出すための力が少ない…というタイプです。
前回ご紹介したのは、食べ過ぎやストレスなど
何となく元気があるような人が該当するタイプでしたが、
今回のタイプは身体が弱っている人が該当しやすいです。
思春期を過ぎて大人になってから、ぽつっとひとつだけ。
炎症はあまりみられない…というようなニキビとなります。
ちなみに前回のタイプは、特に顔のおでこや頬全体にたくさん
炎症を伴うニキビができやすいです。
2021/08/28
ニキビをなくすには?その8
東洋医学では、身体の中に出すべきものが出せずに溜まってしまい
それを何とか外に出そうとニキビができる…と考えられています。
なぜ外に出せなくなってしまうのでしょうか?
まずは、出すべきものが多すぎるタイプからお話しします。
このタイプの原因の一つは、食生活の乱れ・偏りです。
西洋医学と同じで、脂っこいものや甘いものというのは
消化するときに胃腸(東洋医学でいう「脾胃」)に負担がかかります。
なかなか消化できない→身体の中に未消化のものが溜まる→ニキビ
ということですね!
そしてもう一つの原因は、ストレスです。
ストレスは、身体の中のめぐりを悪くさせます。
(気分的にもモヤモヤして、すっきりしませんよね!)
めぐりが悪くなることで渋滞した箇所がパンパンに詰まるため
身体が何とかそれを出さなくては!とニキビを作ってしまうのです。
特に詰まった個所では余分な“熱”が生じるとされ
できるニキビは、赤ニキビや黄ニキビといった炎症を伴うものが多いです。
さらに、あたたかいものは上にたまりやすい、という物質の性質がある通り
身体の上部にニキビがバーッとたくさんできるのも特徴です。
次回は、ニキビをつくってしまう、もうひとつのタイプをお伝えします!
2021/08/21
ニキビをなくすには?その7
“ニキビ体質”ってどういうものなのでしょうか?
今回はそのあたりを突き詰めていきたいと思います!
そもそもニキビって、何なのでしょうか?
ニキビには大きく分けて4種類あります。
①白ニキビ ②黒ニキビ ③赤ニキビ ④黄ニキビ の4種類です。
①白ニキビ…毛穴がふさがって中に皮脂が詰まった状態。
②黒ニキビ…白ニキビの皮脂が酸化して黒ずんだ状態。
③赤ニキビ…①②で詰まっていたところに炎症が起きた状態。
④黄ニキビ…③が悪化して膿が溜まった状態。
これが、西洋医学の皮膚科の知識です。
①から④へ進行していくのがニキビなのです。
では東洋医学的にはというと…
身体の中から余分なものが溜まっていて、
ニキビはそれを外に出す「浄化反応」によるものと考えられています。
西洋医学は、出口である毛穴が詰まったことが起点となっていますが
東洋医学は、身体の中にたくさん外に出すべきものがありすぎることを起点とします。
どちらも、身体の中にに出せずにいるものが溜まった状態と言い換えられますね!
次回は、どうして出せなくなってしまうのか、というお話をします!