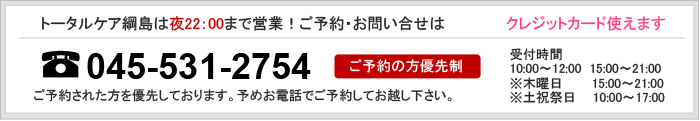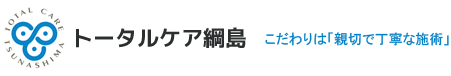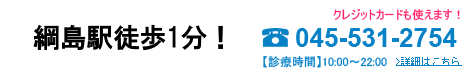新着情報
2021/03/06
更年期障害を治すには~東洋医学の考え方編その3~
前回までに、
更年期障害は「身体の中で火と水のバランスが乱れている」状態で
火は五臓の心、水は五臓の腎の力と置き換えられるとお話をしました。
健康であれば、五臓の心と腎はお互いにバランスを取り合い
どちらかだけが強くなりすぎないように調節しています。
しかし、更年期障害を起こしている患者さんの場合は
腎(水)の力が弱くなっているために、心(火)が強くなりすぎてしまい
ほてりなどの熱症状が出てしまうのですね。
簡単に言えば、水が少ないために、火消しができない状態なのです。
心と腎の調和が上手くいっていない状態なので、
これを〝心腎不交(しんじんふこう)〟といいます。
更年期障害の身体の中の状態…少しイメージできましたでしょうか?
東洋医学では、状態がわかればそれに適した治療方法は明白です。
足らない水を補い、強くなった火の勢いを抑えてあげるのです。
次回はいよいよ治療編をお伝えします!!
2021/02/20
更年期障害を治すには~東洋医学の考え方編その1~
東洋医学に基づいた鍼灸治療では、
まず患者さんの身体の中が
どんな状態にあるのかをさまざまな角度から把握し、
それに合わせて施術を行います。
西洋医学ではホルモンバランスの乱れが原因とされますが、
東洋医学も同様に、身体の中のバランスが乱れてしまった状態といわれています。
更年期障害の特徴的な症状として、
ホットフラッシュなどののぼせがあります。
これは通常よりも身体の中の〝熱(火)〟が強くなっていることを示しています。
健康なとき、例えば運動をしたあとなどでは、〝熱(火)〟が強くなっても、
身体の中にある〝水〟の力で、〝熱(火)〟を弱めてバランスを取っています。
しかし更年期障害では、この〝水〟の力が弱くなっているために
身体の中で発生している〝熱(火)を上手く抑えることができません。
つまり「身体の中で火と水のバランスが乱れている」状態が、更年期障害なのです。
弱くなってしまった〝水〟の力を補い、強くなっている〝火〟の力を弱める…
これが、東洋医学的な更年期障害に対する治療方針になります。
ここでいう〝水〟の力とはいったい何なのでしょう??
汗とは違うものなのでしょうか?…全然わかりませんね!(笑)
安心してください、次回もう少し詳しくお話させていただきます!!
2021/02/13
更年期障害を治すには~基本編~
40代~50代の更年期(閉経期)を迎えた女性は、
ホルモンバランスの変化により
自律神経の働きが乱れ、のぼせや冷えなどの症状がみられやすいです。
これを「更年期障害」といい、
特に、
急にカーッと身体が熱くなる感じのする「ホットフラッシュ」、
またそれに伴い大量の汗をかいてしまうという特徴的な症状があり、
何の前触れもなく起こるため多くの方を悩ませています。
また、最近では20~30代にみられる若年性更年期障害、
男性にみられる男性更年期障害なども増えているといわれています。
この更年期障害に対して西洋医学では、
主にホルモン補充療法という少なくなった
女性ホルモンを補う方法が行われます。
症状によっては、抗うつ薬・抗不安薬なども用いられますが、
さらに漢方薬が用いられることも増えてきています。
漢方薬ですが、実は鍼灸と同じ〈東洋医学〉のものなのです。
…というのはご存知の方も多いですよね!
つまり西洋医学のお医者さんも、東洋医学の効果を認めているのです!
漢方が効くなら、鍼灸も効く!!ということで、
次回からは、鍼灸でどのように治療していくのかをお話ししたいと思います。
2021/02/06
【東洋医学のお話】その5
前々回から引き続き「切診」について。
今回はそのうちの脈診についてお話しします。
脈診ですが、主に使われているのは
橈骨(とうこつ)動脈という手首にある脈です。
東洋医学に限らず、脈拍を数えるときに使われる脈ですね!
脈診の方法にはいろいろなものがありますが、
あまりディープなものをご紹介しても難しいので、簡単なものを。
前回の舌診では、舌の色で身体が冷えているのか熱いのかを診る、とお話しました。
それと同じなのが、脈の数を診る方法です。
病気でなくても脈拍数の変化はみられます。
運動して身体が熱くなれば増えますし、
それに比べて就寝時などは落ち着きますね。
これでまず、全身の熱の有無を見るわけです。
(この他に、実際は脈の強さや打っている深さなども診ます。実はこれが難しい!)
なんだ意外と簡単なんだ!と思われるかもしれませんが、大切なのはここから。
前回お話した舌診やさらに問診からの情報などを総合したときに、つじつまが合うかどうかをみます。
見事つじつまが合えば、その人は〜な状態である、と言えるわけですね!
ひとつのものからの情報だけでなく、いろいろな情報を総合する
…というのが、診断の正確さには重要です!
診る情報は違いますが、このことは西洋医学も東洋医学も共通です。
正確に診断できるからこそ、効果のある治療法として
現代まで長く使われてきているのですね。
そして、この情報を得て総合する力が高ければ高いほど、腕の良い施術者なのです!
なので開業年数が長く、たくさんの患者さんを診ている
治療院を探したほうが、効果的な治療を受けられるというわけです。
東洋医学の診断方法について詳しくお話をしてみました。
これからも少しずつ、みなさんに東洋医学の魅力について
お伝えしていきたいと思いますので、どうかお付き合いください!!
2021/01/30
【東洋医学のお話】その4
前回に引き続き「切診」について。
今回はそのうちの舌診についてお話しします。
舌診は、舌を診ることで全身状態を把握しよう、というものです。
これ「本当かしら…」と不安とあやしさでいっぱいですよね(笑)
簡単な舌の診方に、色というのがあります。
身体が冷えていれば青白く、熱ければ赤いというのです。
普段人の舌をじっくり見ることなんてまずないと思います。
なので、みんなピンクじゃないの?と思われがちですが、
微妙な違いがあるのです!
それを我々東洋医学のプロは見分けていくのです!!
…と偉そうな書き方をしましたが、みなさんも
知らず知らずのうちに似たような診方をされているのです!
例えば、プールに入った後に唇が青ければ
身体を冷やしてしまったのでは?となりますよね。
唇は身体の表面に見えていますが、舌は口の中にあるため、
より身体の内側の状態まで捉えることができるといわれています。
それを上手く使っているのが、舌診なのですね!
舌診ではこの他に、舌の大きさや形、
舌についた苔の状態なども複合し全身状態を把握していきます。